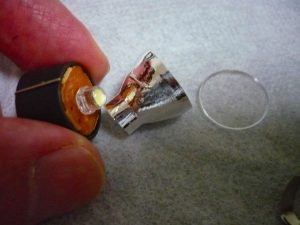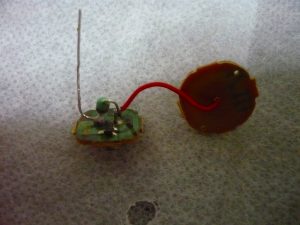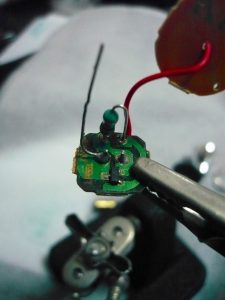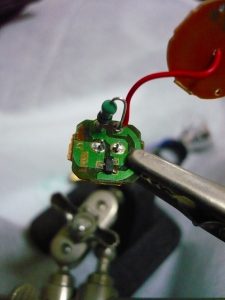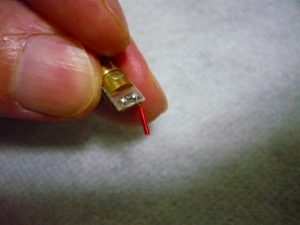ついこの間レーザーポインタを作ったが、レーザーのモジュールが大きすぎることと、秋月のレーザーモジュールの出力が小さすぎて、イマイチであった。
レーザーの光が弱すぎて、実際に使うとプロジェクターの光に負けてしまうのだ。
また、モジュールが大きいので懐中電灯の電池ボックスがしっかり閉まらない。
もう一度完全版を作るために、もう一度作り直した。
まず、高出力、小型のレーザーモジュールである。
Amazonで良さそげなものが見つかった。
2個で¥233円。送料込みで¥496円であり、1個あたりであれば秋月のレーザーモジュールより安い。
また、サイズも小さめでよさそうである。
(購入したのが、2018年10月3日。ただし、10月28日現在売り切れとなってしまった。)
購入したレーザーモジュールは、電池で3Vをかけながら、レンズを回してあらかじめ焦点の調整をしておくと良い。
取り付けたあとでは、調整がちょっと面倒となる。
レーザーポインタを入れるのは、前と同じLEDライト。
100均で唯一単三電池一本で動作するLEDライトである。
中で昇圧しているので、単三電池一本で済んでいる。通常単四電池3本のLEDライトが多い。
まずは、電池を入れるときと同様に開けてみる。
LEDは金属のリングで止められているので、何か尖ったものでひっかけて、そのリングをはずす。
あとで、戻すが見えないところなので、多少変形してもOK。
あとは、ライトのレンズ側から押し出せば、部品がすべて出る。
昇圧回路とLEDが入っているモジュールはこれ。
飛び出している針金をまっすぐにして、モジュールを取り出す
部品は以下のようになっていて、丸い基盤からはプラスの電圧が、針金からはマイナスの電圧がかかる。
裏面をはんだごてで温めて、はんだ吸い取り器でLEDのはんだを吸い取ってしまう。
針金はハンドをとると外れてしまうが、後で使うので取っておくこと。
また、針金がついていた方を覚えておくこと。こちらがマイナスになる。
購入したレーザーモジュールの長い配線を切って、5mm程度残した。
ここで、ビニールの被覆をとる前に赤と黒のどちらの色だったかは、記録しておくこと。
LEDの代わりにレーザーモジュールをはんだ付け。
電源のプラスとマイナスに注意。
針金が伸びている方が、マイナスである。
レーザーポインタとなったので、内部の反射鏡はほとんど役立たずだが、捨てるのもなんなのでドリルで口径を広げて、そのまま搭載した。
これでようやくレーザーの搭載モジュール完成。
前の秋月のモジュールと比べると、今回のレーザーポインタ(右側)の方が非常に明るい。
かかったコストは、\496(レーザー)+108円(懐中電灯)。
1つ当たりに計算しなおして、\296+\108=\356
レーザーモジュールは2つ入りだったので、結局2つも作ってしまった。